庭のとある場所に植えるためのバラを探しています。
条件は、
花色:白
花形:一重またはセミダブル。小輪。房咲き。
開花:繰り返し咲き
香り:中〜強
樹形:シュラブまたはランブラー
耐寒性:USDA Hardiness zone 7a 以下
耐陰性:普通で十分
耐病性:強くないとダメ
樹勢:強いに越した事はない
及び、ランブリング・レクター
と、クイーン・オブ・ザ・ムスクス
野の花の可憐さにも降参です。で、ああ見えて超逞しいんでしょう?いいね〜、いいですね〜。
でもここはもっと真っ白なのがいい。
は、この土地では全く伸びないので、おそらく耐寒性がギリギリなのではないかと思います。(肥料が足りてない?まさか癌腫じゃないでしょうね)今度南向きの石垣の大石と大石の間という、うちの庭で一番暖かい所に植えてみます。最後のチャンスとして。
いっそ別の所用に用意した、
を、ここに使ってしまいましょうか?木の形も葉っぱの濃い緑も好きだし。
でも香りがない、orz、、、
うーん、ここには新雪の香りの無さを補ってくれるような薔薇が欲しいんです。お客さんが門をくぐったら「ふわ〜」っと薔薇が香るように。
いいでしょう?良いじゃないですか。大輪の薔薇は却下。新雪より目立ってはだめです。香りも群香というべき香りがいいんです。小輪で一つ一つの香りは弱いのに、房咲きになって数千も数万もの花が集まったときには周りの空気を満たすような香り。
それにアルバ・メイディランドには、もっとずっと日照条件が悪い別の場所で活躍してもらおうと思っているんですよね。
こういう小輪の薔薇って、庭園素材として必要だと思うんですよ。
古い薔薇には小輪房咲きのツルはたくさんありましたよね。ハイブリッド・ムルティフローラのランブラーなんか。一季咲きですけど。
でも、今はほとんどの木薔薇が四季咲きですから、それと合わせるためにはツルの長さは短くて良いから春以外にも繰り返し咲いてくれないと使いにくいんですよ。
なぜそういう薔薇をもっと作らないんでしょう?
今のブリーダーって一輪一輪がゴージャスな薔薇しか作らないんですか?
大輪の薔薇ばかりでは昭和時代の庭みたいになってしまうでしょうに。
私がずっと欲しいと思っているのは、「返り咲きするランブリング・レクター」みたいな薔薇なんですけど。
私の他にも絶対に需要はあるでしょう?
そうしたら、いました、いました、そういうブリーダーが。
ワーテルローもレーヌ・シャボーも彼の薔薇だったんですね。
ベルギーのルイス・レンズ(Louis Lens)。既に故人でした。残念ながら。
ブランドもののレンズ・ローズっていうのはこの人の薔薇でしたか。実は一つ持っています。ホームセンターで写真に一目惚れして買った、
確かにSurprisingな感じがします。絶対ルゴサだと分かる葉っぱの中から、ある日いきなり巨大化したカカヤン薔薇の一重の花がパッと開くんですよ。花弁の質感のせいか見る人に強烈な白さを印象づけます。でもよく見るとうっすらとピンクが入っているんですよね。
何と言う可憐さ。
蕾は小さいくせに花が大きいので、「えっ?いつの間に咲いたの?」って感じで軽くびっくりします。
咲くと爽やかで明るい気分にしてくれます。
これは、ロサ・ブラクティアタ(カカヤン薔薇)とロサ・ルゴサの原種間雑種のF1ですって。
やったー、そういうの大好きです。
カカヤンは持ってました。枯らしましたけど。原種なのに耐寒性が無いなんて知らなかったんですよ。フィリピンのバラと言う意味の名前だそうです。
その耐寒性のない南の薔薇と耐暑性のない北のルゴサをかけ合わせて、暑さにも寒さにも強くて黒星病にも無縁のバリバリ強いバラを作ったということですね。
でも虫には喰われるんですよね(泣)。
思い出しても腹が立つ事に、今年の春、芽吹いたばかりの所を毛虫の一群に丸坊主にされました。まだ株も小さいから本当に丸裸に。私の目が行き届かなくて申し訳ない事をしました。
でもきっと大丈夫と信じて半日陰の場所に植えたらば、スタートが遅らされたためかつい先日開花しました。
本当に大丈夫か分かりませんよ。耐陰性のデータもないし。ダメだったら速攻救出してもっと日向に植え替えます。この花は日射しの元でこそ美しいと思います。(じゃあなぜ半日陰に植えた?)
それはさておき、ルイス・レンズの作品中から目ぼしい物をピックアップしてみます。
ロザリータ(Rosalita)
隣に植えるバラは、パルフェタムール
 |
| Rosa 'Parfait Amour' |
 |
Rosa 'Rambling Rector'
|
近くには、新雪
 |
Rosa 'Shinsetsu'
|
実はここにどちらかを植えようと思って、野の花
 |
Rosa 'Nonoka'
|
 |
| Rosa 'Queen of the Musks' |
を買ってあったんですけど、いざ咲かせてみたらかなりピンクっぽいので今一。
しかしクイーン・オブ・ザ・ムスクス、名前どおり素晴らしい香りでした。いや〜買って良かった。ここではないけどテラス席の近くでぜひ使いたいです。 |
| Rosa 'Queen of the musks' 蕾のときから香っていたけれど、 咲くや否や無惨にもコガネムシの餌食に |
野の花の可憐さにも降参です。で、ああ見えて超逞しいんでしょう?いいね〜、いいですね〜。
でもここはもっと真っ白なのがいい。
レーヌ・シャボー(Reine Chabeau)か、ワーテルロー(Waterloo)なんか良いのではないかと思ったのですが、苗がどこにも売ってないじゃないですか。なぜですか?人気ないんですか?
スノーグース(Snow Goose)
Bred by David C. H. Austin (United Kingdom, 1997).
Climber, Large-Flowered Climber.
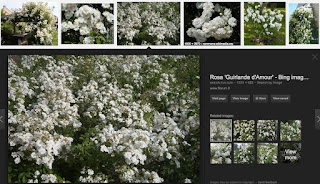 |
| Rosa 'Snow Goose' |
いっそ別の所用に用意した、
アルバ・メイディランド(Alba Meidiland)
Bred by Marie-Louise (Louisette) Meilland (France, 1986).
Shrub. Hybrid sempervirens
 |
| Rosa 'Alba Meidiland' |
を、ここに使ってしまいましょうか?木の形も葉っぱの濃い緑も好きだし。
でも香りがない、orz、、、
うーん、ここには新雪の香りの無さを補ってくれるような薔薇が欲しいんです。お客さんが門をくぐったら「ふわ〜」っと薔薇が香るように。
いいでしょう?良いじゃないですか。大輪の薔薇は却下。新雪より目立ってはだめです。香りも群香というべき香りがいいんです。小輪で一つ一つの香りは弱いのに、房咲きになって数千も数万もの花が集まったときには周りの空気を満たすような香り。
それにアルバ・メイディランドには、もっとずっと日照条件が悪い別の場所で活躍してもらおうと思っているんですよね。
こういう小輪の薔薇って、庭園素材として必要だと思うんですよ。
古い薔薇には小輪房咲きのツルはたくさんありましたよね。ハイブリッド・ムルティフローラのランブラーなんか。一季咲きですけど。
でも、今はほとんどの木薔薇が四季咲きですから、それと合わせるためにはツルの長さは短くて良いから春以外にも繰り返し咲いてくれないと使いにくいんですよ。
なぜそういう薔薇をもっと作らないんでしょう?
今のブリーダーって一輪一輪がゴージャスな薔薇しか作らないんですか?
大輪の薔薇ばかりでは昭和時代の庭みたいになってしまうでしょうに。
私がずっと欲しいと思っているのは、「返り咲きするランブリング・レクター」みたいな薔薇なんですけど。
私の他にも絶対に需要はあるでしょう?
そうしたら、いました、いました、そういうブリーダーが。
ワーテルローもレーヌ・シャボーも彼の薔薇だったんですね。
ベルギーのルイス・レンズ(Louis Lens)。既に故人でした。残念ながら。
 |
Louis Lens(1924-2001)
薔薇について調べるならまずここから
|
ブランドもののレンズ・ローズっていうのはこの人の薔薇でしたか。実は一つ持っています。ホームセンターで写真に一目惚れして買った、
ホワイト・サプライズ(White Surprise)
Hybrid Bracteata, Shrub.
 |
| Rosa 'White Surprise' |
 |
| Rosa 'White Surprise' |
何と言う可憐さ。
 |
| Rosa 'White Surprise' なかなかきれいな形で開かないのはルゴサの血ですか? |
蕾は小さいくせに花が大きいので、「えっ?いつの間に咲いたの?」って感じで軽くびっくりします。
咲くと爽やかで明るい気分にしてくれます。
これは、ロサ・ブラクティアタ(カカヤン薔薇)とロサ・ルゴサの原種間雑種のF1ですって。
やったー、そういうの大好きです。
カカヤンは持ってました。枯らしましたけど。原種なのに耐寒性が無いなんて知らなかったんですよ。フィリピンのバラと言う意味の名前だそうです。
その耐寒性のない南の薔薇と耐暑性のない北のルゴサをかけ合わせて、暑さにも寒さにも強くて黒星病にも無縁のバリバリ強いバラを作ったということですね。
でも虫には喰われるんですよね(泣)。
思い出しても腹が立つ事に、今年の春、芽吹いたばかりの所を毛虫の一群に丸坊主にされました。まだ株も小さいから本当に丸裸に。私の目が行き届かなくて申し訳ない事をしました。
 |
| ポールズが上空を覆ってしまったら ここはもっと日陰になります。 ここに白い薔薇が咲いたら 凄く目立つでしょうけどね 代わりに白いヤマアジサイでも植えますか |
本当に大丈夫か分かりませんよ。耐陰性のデータもないし。ダメだったら速攻救出してもっと日向に植え替えます。この花は日射しの元でこそ美しいと思います。(じゃあなぜ半日陰に植えた?)
というか、これ、ちゃんと育つと2mになるんですか、今更だけどここでは狭いですかね〜、う〜ん。隣(というか上)はポールズヒマラヤンムスク、反対側はエルフルト。一緒に咲いた時マッチしないかもしれません。樹形も育ててみないと分からないですしねぇ。どうせルゴサっぽい丸い茂みになるのではないかと思いますが。
それはさておき、ルイス・レンズの作品中から目ぼしい物をピックアップしてみます。
レーヌ・シャボー(Reine Chabeau)
1994, Hybrid Musk.
 |
| Rosa 'Reine Chabeau' |
白 または 白系、強香、平均花径 3.2cm. 小輪、半八重(花弁数9-16) 春から秋まで断続的に返り咲く
樹高: 80 - 120 cm
USDA zone 6b - 10b.
2倍体
seed:Seagull × Rosa multiflora 'Nana'
pollen:Rosa multiflora 'Nana'
ロザリータ(Rosalita)
1996以前 Hybrid Musk.
 |
| Rosa 'Rosalita' |
薄黄色, 黄色い花心, 白く退色する . 中香、ムスク香
平均花径 3.8cm. 小輪、一重(花弁数4-8) 5.7cm. 大きな房咲き、春から秋まで断続的に返り咲く
大きい、つやのある、暗緑色の葉
樹高:120 - 150 cm
USDA zone 6b 及びそれより暖地
seed:Trier (Hybrid Multiflora, Lambert, 1904) × Surf Rider
pollen:Rosa helenae Rehder & E.H.Wilson
ワーテルロー(Waterloo)
1996以前 Hybrid Multiflora, Hybrid Musk, Shrub.
 |
| Rosa 'Waterloo' |
クリーム. [白 または 白系] 平均花径、2.54cm、小輪、半八重(花弁数9-16)、 八重 (花弁数17-25)、房咲き、春から秋まで断続的に返り咲く
直立型. 灰緑色の葉
樹高:125 to 150 cm
USDA zone 6b through 9b (default)
seedling of Seagull × Rosa multiflora 'Nana'
|
エディ・グリム(Hedi Grimm)
2001以前 Hybrid Musk.
 |
| Rosa 'Hedi Grimm' |
白 または 白系、中香、平均花径 3.8cm. 小輪、半八重(花弁数9-16), 大きな房咲き、春から秋まで断続的に返り咲く
つる性
樹高:180 to 250 cm
USDA zone 6b - 9b (default).
seedling of Seagull × R. multiflora nana
|
ギルランド・ダムール(Guirlande d'Amour)
1993以前 Climber, Hybrid Musk.
 |
| Rosa 'Guirlande d'Amour' |
白 または 白系、強香、平均花径 3.2cm. 小輪、半八重(花弁数9-16), 大きな房咲き、春から秋まで断続的に返り咲く
高性、刺に覆われた、つる性、直立
中くらいのややつやのあるミディアムグリーンの葉
樹高:180 - 300 cm
USDA zone 6b - 9b (default).
耐病性:非常に高い
2倍体
seed:Seagull
pollen:Rosa multiflora 'Nana' × Moonlight (hybrid musk, Pemberton, 1913)
何とまあ!
全部ハイブリッド・ムスクじゃないですか!
しかも、ロザリータ以外は全部、'シーガル' とロサ・ムルティフローラ 'ナナ' の交配。どんだけこの系統に入れ込んだんでしょう?
好きだったんですね、シーガル。分かります〜。私も好きですから。
彼の追い求めた理想のバラの一つは「返り咲きするシーガル」だったんですね。もしくは「返り咲きするボビー・ジェイムズ(Bobby James)」とか「返り咲きするザ・ガーランド(The Garland)」、「返り咲きするランブリング・レクター(Rmbling Rector)」みたいな薔薇。
先生!私達、気が合いますね!
こういう薔薇が欲しかったんです。
彼は他にも色々作ってますけど、特にハイブリッド・ムスク(HMsk)に情熱を傾けたブリーダーだったらしいです。
いいですよねHMsk。
私も気がつけばHMskばかり集めてますよ。良いなと思うと何故かHMskでね。だってここ蓼科では薔薇の咲く6月にドンピシャで梅雨に当たりますから。いくら好きでも花弁が薄くて多くて雨に弱い一季咲きのオールドローズばかり庭に植えてたらこんな悲しい事はありません。
また、こういう高冷地では夏の薔薇も咲きますから。それに秋の薔薇もそれは見事で。ぜひ春以外にも咲く薔薇を選びたいわけです。
それに、(え?消毒ぅ?絶対しないし。)
耐病性が高くないとうちでは生き残れません。HMskは優秀です。
でも疑問なんですけどロザリータとギルランド・ダムール以外は祖先にシーガルとナナしか居ないじゃないですか。これで何でHMskなんですか?シーガルってロサ・モスカータの血が入ってるんでしょうか?
シーガル(Seagull)
1907, Hybrid multiflora, Rambler
 |
| シーガルの画像検索すると半八重くらいの花が多い様な気がしますが うちのシーガルは3年間ほぼ一重です もしかして肥料が足りてないからでしょうか |
ブリーダー:Pritchard (United Kingdom, 1907).
Rambler
白、雄しべ黄色、強香、一重(花弁数4-8)、大房咲き、一季咲き
つる性、マットな明るい緑の葉
樹高:520 - 610 cm
USDA zone 5b(よしよし) 及びそれより暖地、耐寒性あり、極めて強健(OK. Good!)
5倍体(えっ?!)
交配親:
Rosa multiflora Thunb. × Général Jacqueminot (hybrid perpetual, Roussel, 1853)(えっ!?)
|
シーガルの花粉親があの真っ赤な大輪のジェネラル・ジャクミノ?
それは何かの間違いじゃないの?と思えば、この説には異論があるそうです。それはそうでしょう。
原種ムルティフローラは2倍体、ジェネラル・ジャクミノは4倍体
これでは普通なら3倍体になるはずですが?減数分裂時に何かエラーが起きたということで。
大体、5倍体ってのはいろいろと凄いですね。だからあんなに巨大化するんでしょうか。
 |
| Rosa 'Seagull' |
そうはいってもシーガルの種は発芽率は悪かったりするのかもしれません。かなりきれいなローズヒップを鈴なりに付けて秋は見事なんですけどね。
だから「シーガルの実生」と言うワンクッションをおいてから 'ナナ'(多分2倍体)の花粉をかけてみたのでしょうか。それがワーテルローとエディ・グリム。
でも直接 'ナナ'の花粉で発芽したシーガルの実もあって、それにもう一度 'ナナ'を戻し交配したのがレーヌ・シャボー(2倍体)。
'ナナ'の花にムーンライト(2倍体)の花粉で受精させてできた薔薇の花粉を取って、それをシーガルに受粉させたのがギルランド・ダムール(2倍体)。
何と言う執念。というか研究熱心。
本当〜〜〜に、しつこくて熱い性格じゃないとブリーダーなんかやれませんね。そして、マメに正確に記録を取って、整理整頓が得意じゃないと結果なんか出せないでしょうね。
薔薇の倍数性についての記載
http://garden-in-the.rosepink.us/hybridizing/polyploid2.html
'ナナ'は原種のムルティフローラの小型の亜種なのかと思えば、なんとポリアンサで60cmくらいしか伸びない四季咲き。
困ります!そういう紛らわしい名前を付けないでください!
(昔の事だから仕方ないですね)
ムルティフローラの血を引いているのは間違いなさそうですけど、バラ園で偶然発見された交配種らしく祖先は不明。
ロサ・ムルティフローラ 'ナナ'(Rosa multiflora 'Nana')
1875, polyantha
 |
| Rosa multiflora 'Nana' |
白、薄いピンク、 強香、小輪、一重(花弁数4-8)、房咲き、春から秋まで断続的に返り咲く
樹高:30 - 60 cm
USDA zone 6b - 9b (default).
交配親:不明
|
交配が不明ならモスカータの血が入ってたりするかもしれなくて、だからハイブリッド・ムスクの親になれるのでしょうか?
いやいや、どうもそれは無理矢理こじつけても無理っぽいですね。
ハイブリッド・ムスクの栽培
http://mohri.la.coocan.jp/rose/jkrs/38/jkrs3813.html
《引用》
ハイブリッド・ムスクというグループの名前はロサ・モスカータの交雑種という意味を持つが、この場合はそうではなく‘トリアー’を親として(1)秋にもよく咲き、(2)香よく、(3)庭に植えて美しいバラを目指したジョゼフ.H.ペンバートン師とそのベンタール氏などの後継者たちが作出した一連のバラをハイブリッド・ムスクと称したことによる。‘トリアー’の6代前の片親がロサ・モスカータであるから完全に間違っているわけではないが、‘トリアー’の2代前の親はロサ・ムルティフローラであるからむしろハイブリッド・ムルティフローラと表現したほうがいいという意見もある。事実形質(樹形、花形、実)からみてそのほうが納得出来る品種が多い。
ロサ・モスカータ(Rosa moschata)
原種
 |
| Rosa moschata |
ロサ・ムルティフローラ(Rosa multiflora)
原種
 |
| Rosa multiflora |
ハイブリッド・ムスク(HMsk)の系統においては、ムスクと言うのは名前だけで、実はロサ・モスカータの血は薄い。むしろロサ・ムルティフローラの血を引いていて、返り咲き性があって、ムスクの(?)香りがして、トライア(Rosa 'Trier')を祖先に持つ薔薇をHMskと呼ぶってことになったんでしょうか。更に今では別にトライアの血を引いてなくても良いってことに。
トライア(Trier)
1904, Hybrid Multiflora, Hybrid Musk, Lambertiana, Rambler.
 |
| Rosa 'Trier' |
つまりHMskとは、繰り返し咲く、ツルの短いハイブリッド・ムルティフローラのことだと?
そうとでも考えなければレーヌ・シャボーがHMskには分類されないでしょう。多分そういう合意が薔薇業界では得られているんだと想像してます。
そうとでも考えなければレーヌ・シャボーがHMskには分類されないでしょう。多分そういう合意が薔薇業界では得られているんだと想像してます。
では、結局、このルイス・レンズ作の新しいHMskの中からもし選ぶなら?
はい!
ギルランド・ダムール(Guirlande d'Amour)にします。
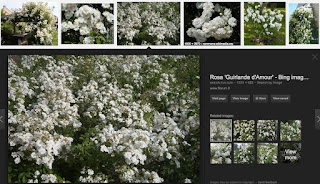 |
| Rosa 'Guirlande d'Amour' |
理由1:私がしょっちゅうお世話になるDave's Gardenで、USDA Zone 6a: to -23.3 °C (-10 °F)での栽培記録有り。岩見沢でも咲いているらしい。イコロにも苗が売っている。耐寒性は大丈夫でしょう。
理由2:この中で一番樹高が高い。寒冷地でも伸びてくれそう。
理由3:耐病性が「非常に高い」。他のも高そうではあるが、そこまで書かれるなら期待しましょう。
理由4:ムスク香とは書いてないが強香と記載。それは無条件に良い事です。例え咲くや否やコガネムシの餌食になっても(泣)。花数が多ければ奴らも喰いきれまい。
理由5:父系祖父に私の大好きな'ムーンライト'が入っている。孫にも期待。
ムーンライト(Moonlight)
1913, Hybrid Musk, Shrub.
 |
| Rosa 'Moonlight' |
理由6:間を挟まずシーガルの直接の実生の子。強そう。期待。
理由7:購入可能。そりゃあそうでしょう。入手できなきゃ話にならないですから。
理由8:色々な所で記載が多い。人気がある。と言う事はメリットがあるからで。
理由9:隣の薔薇がパルフェ・タムール(Parfait Amour)なので、ここはアムール(Amour)つながりで。愛の競演ということで。
パルフェタムール(Parfait Amour)'CHEwsinger'
Christopher H. Warner (United Kingdom, before 2009), Shrub
 |
| Rosa 'CHEwsinger' or 'Parfait Amour' |
紫赤、中心白、小輪、一重(花弁数 4-8)、房咲き、スパイス香、春から秋まで連続的に開花
半光沢性で明るい緑の葉
樹高:250 cm以下
幅:300 cm以内
耐病性:高い
上手く行けば赤紫と白の小輪の薔薇が入り乱れて咲くでしょう、、、
辺りには良い香りが漂って、、、
わーすてき、、、
、、、、
となるいいですねー。
大体、花期が合うかどうかとか、樹形が似合うかどうかとか、葉っぱも似合うかどうか、ツルの太さはどうかとか、手元で咲かせてみないと分からない事だらけです。だからとりあえず買うしかないんですよね。パルフェタムールも情報が少なくて、買ったはいいが正直言ってまだどんな薔薇だか分かっていないんです。まだ咲いてないですし。
こうして、コレクターでもなく、いろんな品種を集めて喜んでいるつもりなんか全然ないのに、手持ちの品種が数ばかり増えて行くんですね。薔薇も、ホスタも。
(うちにズラーッと並んでいるホスタの鉢はそういう訳です。)
 |
| June 14, 2014 |
あ、ホスタで滅びたのは一つだけですけど(グレート・エクスペクテイションズ)、
薔薇は自然淘汰されて着々と数が減っていきますから。
薔薇は自然淘汰されて着々と数が減っていきますから。
はは。


























